危機管理広報とは?マニュアルとメディアトレーニングがポイント

広報PRの仕事は、企業が自分から発信する情報の取り扱いだけではありません。
一般財団法人 経済広報センターの調査によると、企業の広報部門で重要だと思う仕事は、1位が報道対応(77%)で、2位が危機管理(53%)となっています。
思いがけない不祥事や事件・事故、SNSでの炎上など、発生した問題に対してメディア対応をはじめとした対外的な窓口となり、リスクを最小限に抑える危機管理も、広報PRの重要な役割です。
この記事では、企業の広報PRとして押さえておくべき危機管理の対策と、広報担当だけでなく経営者や役員にも必須の「メディアトレーニング」について詳しく解説していきます。
■この記事について
- 読了目安:8分
- ページ数:1ページ
■本記事のサマリー
- 自社の抱えるリスクの把握と「危機管理」のルール化とマニュアル化が重要。
- 場当たり的な初動対応をしたために、長期にわたって会社の評判を落としたり、訴訟問題に発展したりする可能性もある。
- メディアトレーニングとは、公の場で発言する機会のあるスポークスパーソンに対して行う、取材対応のトレーニング。
広報担当に必要なリスク管理とは?事前にできる3つの対策
企業において、何らかの不祥事はいつでも起こり得るものです。
その際、初動対応を間違えたために、消費者やメディアからのバッシングが悪化してしまうケースは珍しくありません。
近年では、単なる業務上の不祥事にとどまらず、企業の販促キャンペーンがSNS上で商品不買運動に発展したり、従業員が録画したパワハラ動画がSNSで拡散されてしまったりと、マスコミ対応とは異なる対策が必要になる場合も考えられます。
危機管理対策として、広報部門が事前にできるリスク管理のポイントは3つです。

ポイント1:平時からのリスク管理
まず必要なのは、自社にはどのようなリスクがあるかを明らかにすることです。
問題が起こってから慌てて対応を考えるよりも、平時にシミュレーションしておく方が、はるかに冷静に効率よく対応策を準備できます。
たとえば飲食業であれば食中毒や従業員の労務管理リスク、製造業であれば工場の生産トラブルや海外支社における訴訟リスクなどが考えられるでしょう。
事例として、2014年に「ペヤングソースやきそば」のゴキブリ混入問題があった「まるか食品」を見てみましょう。
このケースでは、初動対応で混入を否定したうえ、混入写真をSNSにアップした当事者にまるか食品側が圧力をかけたことをTwitterに投稿され、多くの消費者に不信感を抱かせてしまいます。
その後、保健所の立ち入り検査で自主回収を命じられ、メディアから批判的な報道が集中。
結局、リコール保険に未加入だったこともあり、まるか食品は設備の刷新も含めて、数十億円の損害を出すまでになりました。
この初動対応の失敗の原因は複数ありますが、第一に工場の生産トラブルをリスクとして管理していなかった点が挙げられます。
このような潜在的なリスクの洗い出しには、営業や法務、労務など他部門を巻き込んで広く精査することが必要になります。
そのため、事前に経営者・役員会などと連携し、「危機管理広報のマニュアル制定のため」という社内合意を得てからリスクの洗い出しに取り掛かりましょう。
全社を挙げてリスクを精査するためにも、事前の経営陣の承認と理解が重要になるのです。
そもそも、金融庁と東京証券取引所が公表している「コーポレートガバナンス・コード」の原則には「適切な情報開示と透明性の確保」が挙げられています。
メディアから追及されて守備的な対応をするよりも、自社に起こりうるリスクを把握し、積極的に情報開示する攻めの危機管理広報が、ブランドイメージの毀損を回避する一手となるでしょう。

ポイント2:危機管理のルールとマニュアルの制定
つぎに必要なのは、いざ問題が起きた時にどのように対応するかという「危機管理」のルールとマニュアルを制定することです。
企業に起こる問題のほとんどは、突発的な事案です。
自社がSNSで炎上していたことを、マスコミからの取材で初めて気がつくケースも珍しくありません。
慌てて場当たり的な初動対応をしたために、長期にわたって会社の評判を落としたり、訴訟問題に発展したりする可能性もあるのです。
そのような事態に陥らないためには、平時のうちから危機管理対応のルールを決め、マニュアル化して全社で共有しておくことが大切です。
危機管理マニュアルで決めておく内容には、次のようなものがあります。
・問題発生時の初動対応(現状把握・事実確認等の手順と担当者)
・対応メンバー(危機管理委員会)の招集基準と連絡方法
・広報対応の確認(窓口・想定問答の準備・担当者)
・記者会見の手順(会場・発言者・想定問答の準備)
・報道内容の確認や誤報対策、SNS対応、風評被害対応
・社内外への報告方法、謝罪広告の検討 など
これは広報部門の中で決めてしまうのではなく、経営者・役員会の承認を得ながら作成する必要があります。
なぜなら、危機管理委員会の立ち上げやメンバー選定、社内外への情報伝達方法、対応するための予算などは、広報部門だけでは決定できないからです。
また、法務部門や財務経理部門との連携が必要になることも多いため、事前に経営陣の承認と理解を得ることで、スムーズな連携が可能になるでしょう。

ポイント3:メディア対応のトレーニング
突然のトラブルに対して、堂々と冷静に対応できる人間は多くありません。
対策として、平時のうちから、記者会見やインタビューなど公の場での発言に対してトレーニングを行っておくことが重要になります。
なぜなら、トラブル対応のために記者会見を行なったものの、そこでの幹部の発言がさらなる誤解を招き、ブランドイメージの毀損につながる場合もあるからです。
たとえば、東京五輪大会組織委員会の性差別発言では、発言者が記者会見で行った弁明が「さらに差別的だ」と火に油を注ぐ騒動となり、IOCから「男女平等に向けた公約などに反する」と指摘を受ける結果になりました。
また、組織を「守る」という意識が働き、メディアの質問に明確に答えられなかったり、説明が二転三転したりして、記者会見に失敗するケースも珍しくありません。
たとえば、2018年の日大アメフト部の危険タックル問題では、初動対応で「指導者の言葉を選手が曲解した」というスタンスを取ったものの、選手個人が反論の記者会見を行い、さらに日大首脳陣が選手の会見内容を否定するという混乱をあらわにし、「危機管理広報の失敗例」として酷評されるに至りました。
このようなメディア対応の失敗は、緊急記者会見などの急なメディア対応に慣れていないことが原因の一つと言えるでしょう。
次の章からは、有事の対応に欠かせないメディアトレーニングについて解説します。
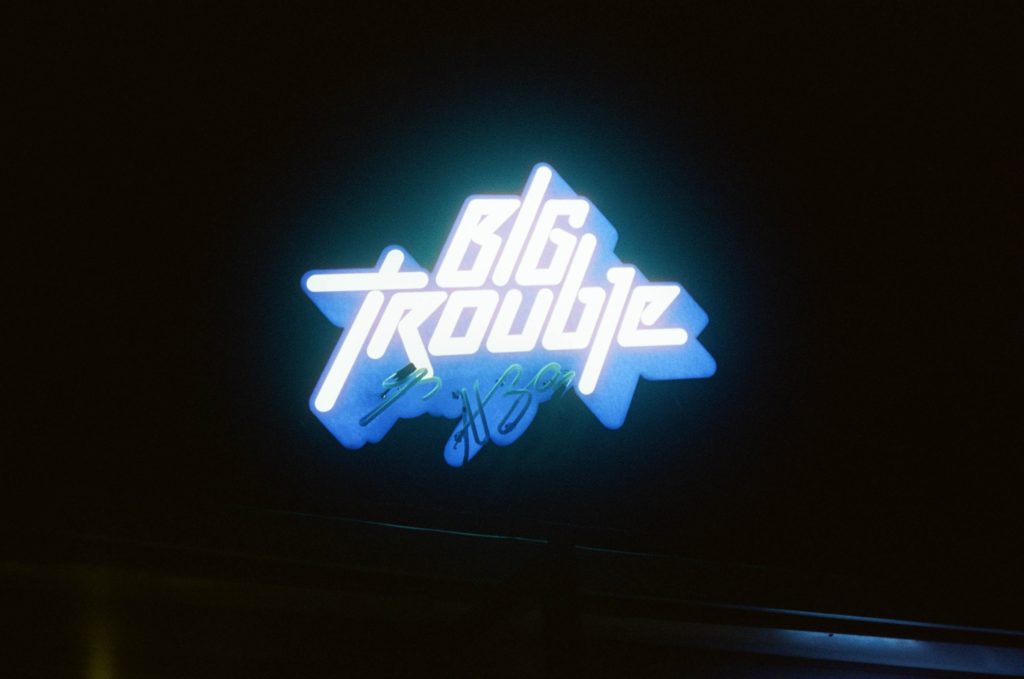
危機管理に向けたメディアトレーニング
メディアトレーニングとは、公の場で発言する機会のあるスポークスパーソンに対して行う、取材対応のトレーニングです。
対象者として、社長や幹部、事業責任者、広報責任者などが挙げられます。
企業に対するメディアの取材内容は、基本的に企業側でコントロールできません。ときには、記者会見中の目立つ発言だけを切り取って編集されてしまう場合もあります。
そのため、メディア対応時の不用意な発言によってブランドイメージの毀損につながらないよう、危機管理の一環としてもメディアトレーニングは重要な要素なのです。
すでに欧米の企業の大部分では、幹部社員と将来の幹部候補にメディアトレーニングを受講させています。
日本国内の企業でも、全体平均で16.4%が継続的にメディアトレーニングを行っており、なかでも「電力・ガス」「食料品」「運輸・倉庫」といった人々の生活に直結する業種のトレーニング実施率は、50%以上です。
メディアトレーニングの内容は、大きく3つに分かれています。
・メディアに対する話し方や立居振る舞い
・取材に対する事前準備
・実際の取材や記者会見を模した演習
記者会見の演習では、通常の記者発表と、有事の緊急記者会見という2パターンの訓練を行い、スポークスパーソンの対応力を磨いていきます。

取材対応に欠かせないメディアトレーニング
ブランドイメージを守るためのメディアトレーニングは、有事の際の記者会見だけでなく、平時のインタビューやプレス発表でも役立つテクニックです。
なかには、販促担当や採用担当など、メディアで発言する可能性がある社員全員にメディアトレーニングを受けさせている企業もあります。
また、性差別や人権問題などのトラブルが起こった際に、責任者の世代によっては、現在の価値観とは相容れない発言をしてしまうケースが散見されます。会社のブランドイメージを守るためにも、積極的にトレーニングを受けておくことをおすすめします。

いかがでしたでしょうか? 今回は危機管理広報についてお伝えしました。
現代社会は一億総監視(評論)社会と形容されるように、SNSなどで個人でも容易に情報発信ができる時代です。
企業の不正はこれらツールによってようやく明るみに出ることもありますが、反面、思わぬ炎上に巻き込まれることも多々あります。こうした社会の流れは止められず、であるからこそ、あらゆる企業は自社の抱える潜在的リスクにまで気を配ることが重要になります。
有事の時だけでなく、日頃から社内の意思統一を図り、準備しておくことで、最悪の事態を免れることも少なくありません。
ぜひ今回の記事をきっかけにして、自社の潜在的なリスクについて、社内を巻き込んで検討いただければと思います。
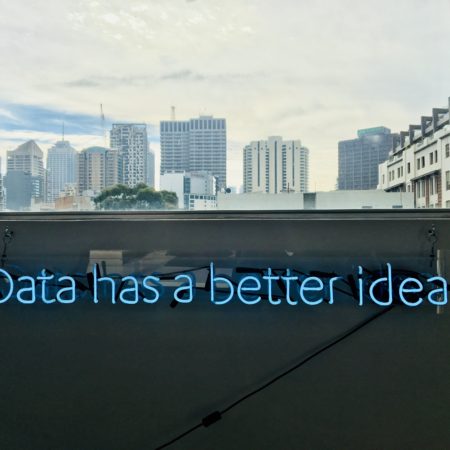








この記事へのコメントはありません。